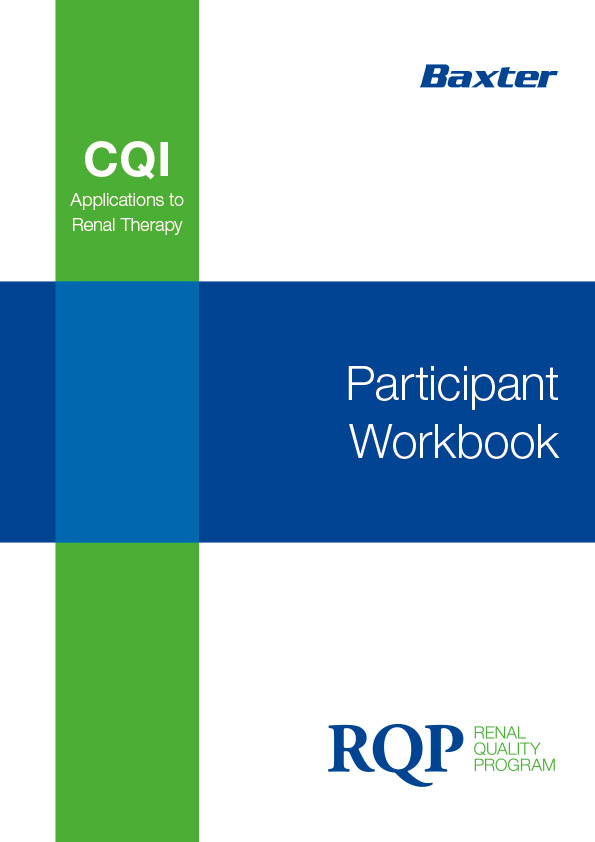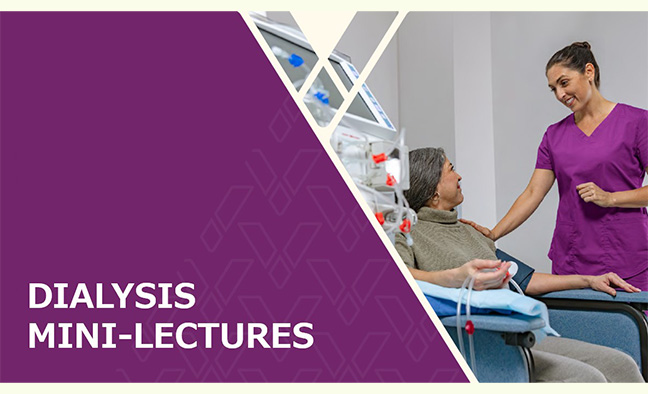本ページでは抜粋版の動画をご視聴いただけます
特集:CQI活動
学会も取り組み始めた「CQI活動」のコツについて、経験豊かな講師が解説くださいます。
CQI実践のためのHow toテキスト「CQIワークブック」、各種分析シートもご活用ください。
(講師のご所属・職位等は動画収録当時のものです)
はじめての腹膜透析
腎代替療法のひとつである腹膜透析(PD)に関して、基本的な知識を習得できます
慶應義塾大学医学部 血液浄化・透析センター 森本 耕吉 先生
-
腎代替療法におけるPDの役割と特徴
-
腹膜透析処方の基本的な考え方
-
適正透析を目指したPD処方の調整と自動腹膜透析(APD) Part1
-
適正透析を目指したPD処方の調整と自動腹膜透析(APD) Part2
-
腎代替療法の再選択と最適化 Part1
-
腎代替療法の再選択と最適化 Part2
-
腹膜炎に立ち向かう Part1
-
腹膜炎に立ち向かう Part2
カテーテル挿入術
PDカテーテルは腹膜透析液のアクセスルートであり、腹膜透析の要です。
そのためトラブルを予防できる理想的なカテーテル留置を行うことが極めて重要です。
その結果としてカテーテルの高い開存率、PDの治療継続率の向上に寄与します。
白報会王子病院 腎臓内科 窪田 実 先生
-
PDカテーテル留置術
-
あってはならない術中合併症
-
カテーテル関連合併症の外科的治療
かかりつけ医と腹膜透析
かかりつけ医の先生が腹膜透析(PD)を始めたきっかけや
腹膜透析の基礎から「いま」が分かる情報を掲載しています。
-
開業医でも十分可能なPD管理
飯田橋西口クリニック 原澤 信介 先生 -
江戸川Hub&Spokeモデル 病診連携の一例
訪問診療わっしょいクリニック 緒方 彩人 先生 -
かかりつけ医・在宅医におけるPD診療の取り組み「訪問診療編」
楠本内科医院 楠本 拓生 先生
変わる!腹膜透析のあたりまえ
実際に腹膜透析診療に取り組まれている非専門医の先生方のお話をご紹介します。
-
愛し野内科クリニック
岡本 卓 先生 -
猿払村国民健康保険病院
日本腹膜透析学会連携認定医
佐藤 克哉 先生
オンデマンドでのラーニングコース


トラブルシューティング
-
非感染性合併症:注排液不良
日本赤十字 さいたま赤十字病院
星野 太郎 先生 -
腹膜透析の体液管理 総論
東北医科薬科大学病院 石山 勝也 先生 -
PDHD併用療法 Part1
順天堂大学医学部附属練馬病院
狩野 俊樹 先生 -
出口部管理 前編
関西電力病院 戸田 尚宏 先生 -
自動腹膜透析(APD) Part1
症例ベースで考えるAPDの活用
慶應義塾大学医学部 森本 耕吉 先生
地域連携 医療福祉制度 他
-
PDにおける遠隔治療の可能性
慶應義塾大学医学部 森本 耕吉 先生 -
アシストPDを支える地域連携
日本赤十字社医療センター 栁 麻衣 先生 -
腹膜透析における訪問看護
日本財団在宅看護センター ひまわり
片岡 今日子 先生
併用療法から血液浄化へ
-
PDHD併用療法PARTⅠ(総論編)
順天堂大学医学部付属練馬病院 腎・高血圧内科
狩野 俊樹 先生
-
各種ガイドライン
・国内・ISPD(国際腹膜透析学会) - 透析患者の課題とこれから
教育講座情報
透析療法の理解を深めるため、様々な教育講座が受講いただけます
-
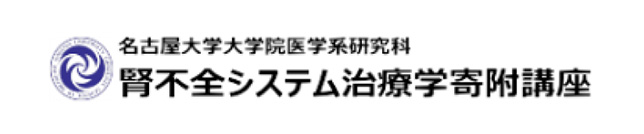
寄附講座:腎不全システム治療学寄附講座/名古屋大学(nagoya-u.ac.jp)
腎不全腹膜透析セミナー:BSJNU(nagoya-u.ac.jp) -
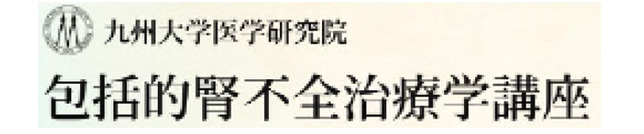
寄附講座:包括的腎不全治療学講座 | 九州大学医学研究院(kyushu-u.ac.jp)
※各種セミナー案内は上記リンク内をご確認ください。 -
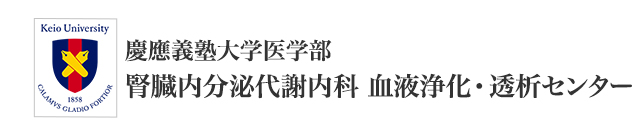
慶應腹膜透析研修プログラム「KEIO PD TRAP」
KEIO PD TRAP参加登録:KEIO PD TRAP参加登録システム(google.com)
- お問い合わせ先はこちら
- 株式会社ヴァンティブ メディカルアフェアズ部
〒108-0023 東京都港区芝浦三丁目4番1号 グランパークタワー30階
Email: [email protected]
 日本の承認内容に基づき日本国内で使用される製品の情報です。 |
日本の承認内容に基づき日本国内で使用される製品の情報です。 |